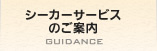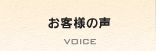捨てる女 内澤旬子
2015年2月27日 カテゴリー:雑記
「突然あたしは何もない部屋に住みたくなった」。
そのサブタイトルから、断捨離系の本かと思われたが読み進むうちに著者が非常に深い濃い人生を歩まれた方なのだと知る。
著者、内澤旬子の職業、イラストルポライターで生活が成り立っている人たちはほんの一握りの世界なのだろう。1冊の本にするまでには膨大な資料と時間を必要として、取材費はかけるほど得るものはあるのだろうが、ではその本が売れるかの約束は全くない。
本をこよなく愛する人、装丁家としても、美しい本とはなんぞやと、活版印刷や革なめしの歴史を調べ、世界各地の希少な本を買いまくり、こんな本が出来ないか面白そうな素材も買いまくる。
海外に出かけるたびに集めた品は手漉き紙、インドの素材、装丁が美しいとされるチェコの本。初期合成樹脂、牛の血を固めた表紙の祈祷書、銀細工の箱入りコーラン、乳香、岩塩、パルミラ椰子の葉っぱ、モロッコタイルの欠片、アムハラ文字のコカコーラの蓋、化石、蜜蠟、太鼓革・・・。
古書マニアは、いつか本を作る時にこれらの材料がすべて使用出来ると信じていたらしい。アンティークに仕上げようと汚れたいわゆるガラクタを大量に購入し、街を彷徨い拾い集めるのだった。
故、植草甚一のように生涯、モノを手放さず愛し続けられる人もいるが、愛してやまないモノと決別する時がやってきたのは肉体と精神の疲労、著者が離婚と乳がんになったことがきっかけだったという。
2011年の震災を経験し、捨てる女はヒートアップし、最終結論はさらばトイレットペーパーと、日本人がおそらく100年くらいはかたくなに守り続けてきた「尻を紙でぬぐう」習慣をも捨て、ついぞイラン人が使用するアーフターベという洗浄器を独自に作成する。
どれだけ共感出来ても、自分には出来ること、出来ないことがある。
そして、モノを捨て去ることの本髄とは何ぞやと関心するばかりである。
時の流れと共に共感することも変化し、それらを維持する体力も経済力も必要になる。モノは呼吸し、スペースを奪い、混乱をきたすこともあるだろう。
かつてこだわり続け、人生を共にしたモノとの決別は容赦なく究極にシンプルに。かなぐり捨てた先には一体何が見えてくるのかが書かれている。
私自身、離婚の際に大量のスクラップブックを処分した。それは気になった内容の新聞、雑誌の記事の抜粋である。無論、これらが何かを生み出したわけでは全くない。
新聞の号外を1980年代から、なぜか集め始め、必ず街頭でゲットし新聞記者でもないのに未解決事件シリーズの資料を独自に集めていた。いやはや全く何がしたかったのか自分でもわからずお恥ずかしい限りである。
タイトルは過激にも思えるが、仕事への真摯なまでの情熱を持った人であり、美しいモノを創り上げるには追及する美学と目に見えない努力、それでも報われないことにめげないことであろうか。
人間はモノを喰らい、身を纏い、知を得るために死ぬまで多くのモノを所有し続ける生き物である。所有するモノは生き様の欠片のようで簡単に捨てる事など出来ない。だからいつまでもそばに置いておきたいのかもしれない。
どうやら、これまでの断捨離本とは全く毛色が違い、アーフターベー然り、この本を完全に読み解くには前作の「世界屠畜紀行」「買い喰い 三匹の豚とわたし」を読まねばなるまいと思うのだった。
「捨てる女」 著者 内澤旬子 本の雑誌社