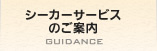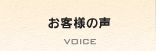謎のあの店
2014年6月12日 カテゴリー:雑記
商いとは万人に門戸を広げ、どれだけ創意工夫しても、全ての店が盛り立っているわけでない。謎の店とは、賑わいのその隙間にひっそりと身を隠しながら、君臨しているものである。
だが暮らしの中に溶け込み過ぎて、一体いつからやっているのか。
その静けさから疑問に思い始め、果して経営出来るほどの客が入っているのだろうか。
何より気になるのが、その店内はどんな風で、店主は一体どんな方であろうかと。
そう思いつつ訪ねる機会もなく、あっという間に数十年が過ぎ行く。
そして、その謎の店が、今も変わらずそこに健在していることに驚くことがある。
取り急ぐ案件ではないが、心のどこかにひっかかる謎。
勝手なお世話であり、人によってはどうでも良い心の霧。
それを晴らすべく著者である漫画家が長年謎に思っていた店への潜入調査を行い、
その内容を漫画にしたタイトルが「謎のあの店」という。
本来、店とは客がいて賑わい、店主の気性と相まって気の流れのようなものが生まれ 何の不信も持たず、そこに立ち入ることがナチュラルに出来るものである。
そんな中、偶然立ち寄った街で、謎のオーラーを充分過ぎるほど放っていた店を発見する。
飲食店はこの店しかない立地でありながら、客はいない。
入店して思う。
これまでの気の流れのようなものが全く感じられなかった。
どんなシチュエーションでも対応出来るナチュラリーな私が 不安を覚えたのは、店内に張られたカレンダーが数年前のままで、置き時計が止まっていたことだった。
醸し出す店内のムードはレトロチックを遥かに超え、この空間をインスタグラムでアップしたらきっと素敵に違いないだろう。
店主は気配を消しながら奥にいた。
それは、そこに何時間いても許されるような時間に思えた。
都会の喧騒の中で、こんな風にひっそりと時が止まったように商いをされていることに
感動を覚えるのだった。
かつて、若い頃から謎に思っていた小さな老舗のバーがあった。
煉瓦の外壁は木々に覆われ、ボンヤリとしたキャンドルのような灯りが窓から映し出され、
一度入りたいと思い訪ねると、更地になってしまっていた。
ネットのない時代だったので入店しないと情報が探れず、消え去ると残念に思う。
ビル全体が廃墟のようになっている姿も美しく、だが、もうその正確な場所さえ覚えていない。
入店して思ったのだが、謎を知ったとたんに、もはやその店は謎という匂いをかき消す。
店を出て振り返ってみると、しっかりと気のオーラに包まれているように思ったのは何故だろう。
そして、謎を解明すると、この作者のように。
次々と謎の店へと出向きたくなってしまうのも何故だろう。
「謎のあの店」 著者 松本英子